 |
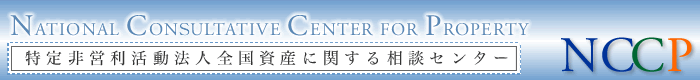 |
 |
|
|
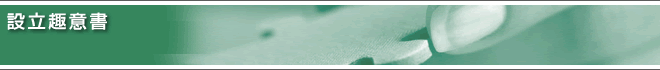 |
設立趣意書
我が国の戦後復興以降の目覚ましい経済の発展は、多くの国民に豊かな生活をもたらしました。一方で今後、我が国は先進国に類を見ない早さで少子高齢化社会を迎えようとしています。このことから国民一人一人が、今後の生活基盤の整備を、自己責任を基本に自助努力による資産形成及び運用、保全を行う必要があると考えられます。
そこで、高度な知識と豊富な経験を有する我々有志は、自己責任の生活基盤の礎としての資産。つまり将来の生活安定の為の貯蓄、居住用財産や収益物件の保有などの財産。又居住用財産の購入及び住宅購入における借入金、収益物件の購入及び建築による借入金などの負の財産も含め、これらの財産形成及び相続又は贈与による財産承継などを、幅広く資産と定義することとし、これら資産に関する、誤った認識や勉強不足・情報不足によって、これまでに起こったトラブル。
例えば、相続問題に関して言えば、被相続人と相続人の見識の相違による相続対策の準備 不足によって、相続発生後十数年に渡って遺産相続についての親族間での争いが続いてい
るケースや相続発生後数十年も土地の名義変更が行われていないケース。又、誤った認識 に基づいて行った親子間の資産贈与によるトラブルの発生。又高齢者層においては、豊か
な老後、つまり自分の思い描く老後生活の実現の為に資産を構築し、その資産を活用して 豊かな老後を過ごす予定であったが、病気や怪我により寝たきりになってしまったり、痴
呆が進み、自ら財産管理が不可能となり、代わって財産管理を行う親族との意思疎通の不 足から、思い描いたような老後をすごせないケース。
青年層においては、雇用制度の変革によって、これまでの終身雇用制や年功序列による昇 給制度が見直されたことなどにより、住宅ローンの返済に困窮したり、住宅購入の為の資
金準備や借り入れ計画の見直しに迫られ、購入時期の変更を余儀なくされたりするケース。 又公的年金制度の支給開始年齢の見直しや保険料負担のあり方など、今後の制度改正によ
っては、可処分所得の減少も予測され、綿密な生活設計を立てて資産形成を行わなければ、 安定した生活が営めないといったケースも考えられます。
現在の我が国は、情報化社会と言われ、インターネットの普及や多数のマネー雑誌の刊行 などにより情報を収集するのは容易になりました。しかしその一方で、効率的な資産形成
及び資産活用、円滑な資産承継を行う為に、各個人及び団体が、多くの情報の中から必要 な情報を的確に抽出し有効活用するためには、知識と経験を必要とします。しかし多くの
個人及び団体がそのような知識を習得し、経験を積んでいるとは考えられません。 そこで、高度な知識と豊富な経験を有する我々有志は、「全国資産に関する相談センター」
を設立し、資産に関する幅広い分野で、トラブル事例の調査研究を、ホームページ上で の掲示、各地での勉強会開催を通じて、広く情報公開する。
更に、資産に関する幅広い分野での知識や問題解決に関する試験を行い。合格者について 「資産コーディネーター」として認証し、全国各地に相談窓口を設け、「資産コーディネー
ター資格」を有した相談員によって、資産に関する様々な問題を抱える不特定多数の個人・ 団体等を対象に、資産に関する専門家による問題解決への助言及び支援に関する事業を行
い、安心できる豊かな暮らしの実現を推進し、以って福祉の増進、社会教育、健全な町づ くり等の公益の増進に寄与する事を目的として活動する事とする。
設立までの経緯
ファイナンシャルプランナー、税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任、一級建築士など資産に関するアドバイスや実務を生業とする有志が、全国各地で開かれる各種研修会への参加などを通して交流を深め情報交換を行うなどして、各々の知識を深め資産に関する業務に携わってきました。
意見交換や情報交換を活発に行うにつれて、それぞれの専門家に相談に来られる一般の個人及び団体が、トラブルが発生して初めて事の重大さに気付き、切羽詰まった状態で相談にこられるケースがほとんどであるという事が判明しました。そこで我々有志はめまぐるしく変わる社会環境及び法律に連携して対応し、広く公益に寄与する為に、各有志がこれまでに関った資産に関するトラブル事例調査研究の結果を公表し、問題発生を防ぐ為の事前対策及び問題発生後の円滑な解決策を考案する為に、情報交換のネットワークを全国に構築し、資産に関する悩みを抱える不特定多数の個人及び団体の相談を受け付ける窓口を設け、気軽に相談に訪れられる組織を形成する事を決意し、特定非営利活動法人として活動することで、広く公益の増進に寄与する事として団体組成する運びとなった。
|
|
 |
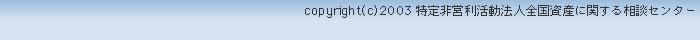 |
|
 |